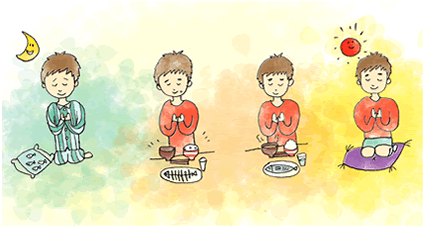大願寺のサイトは、”All in One SEO Pack”というプラグインと、Google Analytics を連携させています。
現在サイトの更新中もあって、自分自身のアクセスが非常に多くなってしまい、アクセス解析に問題がでてきてしまいます。
そこで、自分のアクセスを遮断するために、”All in One SEO Pack”がインストールされているディレクトリにある、
/wp-content/plugins/all-in-one-seo-pack/aioseop.class.php
の一部を修正しました。
現在の、”All in One SEO Pack”のバージョンは”1.6.15.3″ですが、これだと406行目に
“if(!is_user_logged_in()){“
を追加して改行し、429行目に
“}”
を追加しました。
これで自分のアクセスが除外できるはずです。
function aiosp_google_analytics(){
global $aioseop_options;
if(!is_user_logged_in()){/* この行を追加 */
?>
<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', '<?php echo $aioseop_options['aiosp_google_analytics_id']; ?>']);
<?php if ( !empty( $aioseop_options['aiosp_ga_multi_domain'] ) ) {
?> _gaq.push(['_setAllowLinker', true]);
<?php }
if ( !empty( $aioseop_options['aiosp_ga_domain'] ) ) {
?> _gaq.push(['_setDomainName', '<?php echo $aioseop_options['aiosp_ga_domain']; ?>']);
<?php } ?>
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
<?php
}/* この行を追加 */ ?-->