トリオ・ロス・ファンダンゴスの詳細は→こちら
ひかり2013年08月号


弁栄聖者 今月の御道詠
国おもい 仏をしたう 朝な夕な
日の出で入りの かたぞこいしき仏蹟参拝 航海中『日本の光』
コンテンツ
03 光明会各会所年間行事
04 聖者の俤(おもかげ)其三十二 中井 常次郎
06 根源(アルケー)に還る その2 河波 定昌
09 感動説話「裸で生れて」 明千山人
10 子供といっしょに学びましょう 42
12 光明主義と今を生きる女性 内藤 規利子
14 光り輝く淨土への道75 山上 光俊
18 能生法話「一枚の写真」 辻本 光信
19 山崎弁栄記念館開館のお知らせ
20 お袖をつかんで 吉水 岳彦
「第十五歩 意味があること」
22 仏力と易行ということ その3 佐々木 有一
26 ゴエンプロジェクト ─ミャンマーを訪問して─
花房 尚美
28 聖者の霊筆 その10
30 写仏のすすめ
32 支部だより
32 第37回大巌寺別時念仏会ご案内
37 図書案内
38 特別会員及び賛助会員のお願い
39 財団レポート・清納報告・こちらひかり編集室
仏力と易行ということ ─無礙光の序説として─ その3
関東支部会員 佐々木 有一
三、易行品
いよいよ「易行品」に入りますが、これが説かれる前に、安易にやすきにつけばよいというものではない、それなりの覚悟をもって承るべし、とクギをさすことから始まります。
阿惟越致地に至る者は諸々の難行を行ずること久しくしてすなわち得べきも(長い長い難行を乗り越えないと初地に入いれない)……この故にもし諸仏の所説に易行道の疾く阿惟越致地に至ることをうる方便あらば、願わくはためにこれを説きたまえ。
これに対し龍樹は仏道は身命を惜しまず昼夜精進して頭燃をはらうごとく(髪の毛の燃えるのをはらうごとく)すべし、方便を求むとは怯弱下劣の言である、要するにだらしない弱虫のいうことであると叱責します。しかし、
汝もし必ずこの方便を聞かんと欲せば、いままさにこれを説くべし。
といいます。本気で聞いて実行する覚悟があるならば、という念押しです。そして有名な一句をいいます。
仏法に無量の門あり。世間の道に難あり易あり。陸道の歩行はすなわち苦しく、水道の乗船はすなわち楽しきがごとし。菩薩の道もまたかくのごとし。或いは勤行精進する有り、或いは信方便をもって易行にして疾く阿惟越致に至る者有り。
(十方十仏章)
そしてまず十方の十仏、たとえば東方の善徳仏などの名を挙げ、
かくのごとき諸々の世尊は今現に十方にまします。もし人疾く不退転地に至らんと欲せばまさに恭敬心をもって執持して名号を称すべし。
と勧めます。宇宙の東西南北等のどこにいても仏は十方にましますので衆生はその仏の名を称することができます。そしてこの十方十仏の偈の最後に、現にましますこれら十仏は、実は過去無数劫の海徳仏という仏によって発願し、その仏力によって成仏したのだと明かされます。過去無数劫とは無始無終の無始と同じであり、在り通しの本有ということと同じでしょう。
過去無数劫に仏あり、海徳と号す。この諸々の現在仏は、みな彼に従って願を発せり。(海徳仏は)寿命量あることなく(寿命無量)、光明照らすこときわまりなし(光明無量)。国土はなはだ清浄にして、名を聞いて定んで作仏せん。
そして、
今現に十方にましまして具足して十力を成ず。
という原文が続きますが、これは今十方に現存する諸仏がこの海徳仏の力によって仏の十力を成就された、の意味でしょう。
この故に稽首して人天中の最尊(海徳仏)を礼す。
と。稽首とは五体投地接足作礼のことで最高の礼拝です。
(弥陀章)
この十仏以外の仏菩薩の名を称えて初地に至ることができますか、との問いに答えて弥陀章がはじまります。まず矢吹慶輝訳「国訳一切経」から本文の流れをみておきます。
阿弥陀等の仏及び諸々の大菩薩あり、名を称して一心に念ずればまた不退転を得。さらに阿弥陀等の諸仏ありまたまさに恭敬し礼拝してその名号を称すべし。今まさにつぶさに説くべし。無量寿仏・世自在王仏(とつづいて百七番目の)宝相仏(まで列挙され)・この諸々の仏世尊、現に十方の清浄世界に在す。みな名を称して憶念すべし。阿弥陀仏の本願はかくのごとし。もし人われ(阿弥陀仏)を念じて名を称し自ら帰せばすなわち必定に入り阿耨多羅三藐三菩提(無上正等正覚)を得んと。この故につねにまさに憶念すべし。偈をもって称讃す。
この文章に実は二つの読み方があります。一つはいうまでもなく上にみた読み方ですが、もう一つは親鸞の『教行信証』行巻の読み方です。しかも読み方の違い、つまり文点の置き方の違いが二箇所もあります。まず、
阿弥陀等の仏及び諸々の大菩薩あり、名を称して一心に念ずればまた不退転を得。さらに阿弥陀等の諸仏ありまたまさに恭敬し礼拝してその名号を称すべし。
については共通していますが、その後の「今まさにつぶさに説くべし」の内容(対象)を、百七仏の全体とみるか(国訳の立場)、仏名の列挙をいったん無量寿仏できって「今当具説―今まさにつぶさに説くべし」の対象は無量寿仏(だけ)だとみる立場(親鸞の『教行信証』行巻)の二つです。もっとも矢吹博士も易行品全体からして阿弥陀仏が重要な位置を占めており、阿弥陀仏信仰と密接な関係があることは特記しています。
もし後者の場合は世自在応仏以下の百六の仏は、仏名列挙の後に出る文章、
この諸々の仏世尊現に十方の清浄世界に在す。みな名を称して憶念すべし。
(文章A)
で描写されるところの仏だと考えることになります。そして(文章A)に続く、
阿弥陀仏の本願はかくのごとし。もし人われ(阿弥陀仏)を念じて名を称し自ら帰せばすなわち必定に入り阿耨多羅三藐三菩提(無上正等正覚)を得んと。
の文章についても親鸞は文章Aと一緒にして文点を改め(読み換え)ます。すなわち、
この諸々の仏世尊現に十方の清浄世界に在してみな阿弥陀仏の本願を称名憶念することかくのごとし。
となります。これが第二の読み換えです。本願の内容自体(もし人我を念じて名を称し…)は変わりません。このように読めば百六仏は阿弥陀仏を称名憶念して成仏したということになります。だからこそ阿弥陀仏を「この故につねにまさに憶念すべし」と結んで次の阿弥陀仏を称讃する偈につながっていくと解するわけでしょう。
この箇所の解釈については親鸞が独得の読み方をしていることもあって(また親鸞は法然と違って易行品を含む『十住毘婆沙論』を正依の経論と定めたことが基盤にあって)浄土真宗関係の文献には種々の論考があると思われます。しかしあいにく筆者は未見であり一知半解の謗りはまぬかれませんが、このくだりに関しては阿弥陀仏と他の百六仏を並列的に扱うのではなく、格別に抜き出して阿弥陀仏の特別性を重視する立場に歩み寄りたいと思います。
一つの問題点は「今まさにつぶさに説くべし」の対象は「無量寿仏」とあるのにそれが阿弥陀仏のことであると理解してよいのかという問題です。「阿弥陀経」に、釈尊は極楽にまします彼の仏は何が故に阿弥陀と号すや、と自問して、光明無量の故に(アミターバ)、また寿命無量の故に(アミターユス)、と自答されます。「無量寿経」や「観無量寿経」も阿弥陀仏を主人公とした経典です。一仏二名は他に例がないそうですが要するに無量ということが阿弥陀の本義でありますから、この本文の「無量寿仏・世自在王仏・…」の列挙の筆頭の無量寿仏は阿弥陀仏のことと了解しても誤りとはいえないでしょう。
では何故阿弥陀仏を特別に扱う立場に同調するかについて私見を述べます。
一つには仏名の順序のことです。世自在王仏が無量寿仏の次に置かれています。これは周知のごとく「無量寿経」では法蔵菩薩が世自在王仏の御許で発願し、修行をして成仏して阿弥陀仏となるわけですから順序が逆です。龍樹の信仰対象が阿弥陀仏に傾斜していることの反映でしょうか、また別の経典など他の理由があるのでしょうか。
次にさきの阿弥陀仏の本願にかかわって「この故につねにまさに憶念すべし」の文章に続いて、「偈をもって称讃す」と三十二行の長い偈をもって阿弥陀仏が称讃されます。この偈の要点は後述しますが阿弥陀仏が格別の立場にあることは龍樹の本文からも肯定せざるを得ないと思います。
第三は、阿弥陀仏をこのように位置づけますと、阿弥陀仏以外の諸仏はもと衆生であり阿弥陀仏の本願を信じて憶念し正覚を成じたということになります。この阿弥陀仏は本有無作の本仏としての阿弥陀仏でなければなりますまい。これは弁栄聖者独自の仏身観、本仏としての阿弥陀仏観に調和しています。但しそのよって来たる所以は同じではないと思います。
親鸞においては至誠心の解釈にみられるような人間無力観・絶対他力観と、それに表裏一体をなすともいうべき弥陀一仏への徹底的傾倒に由来するのではないでしょうか。もっとも、遠くから管見しての謬見にすぎぬかもしれません。
一方、弁栄聖者の阿弥陀仏本仏論では、法蔵菩薩十劫正覚の阿弥陀仏は本有無作無始無終の本仏阿弥陀如来の迹仏であるとみる立場であります。しかもこの本迹二仏は不二であります。ここで詳述は控えますが(拙稿「大ミオヤの発見――新しい公理をたてた弁栄聖者」参照)、要するに無量寿経「如来光明歎徳章」の「仏(釈尊)、阿難に告げたまわく、無量寿如来の威神光明最尊第一にして諸仏の光明及ぶこと能わざる所なり」の一文が教証となります。易行品の阿弥陀仏を特別な存在とみる点は親鸞のそれと似ていますが、こちらは本仏阿弥陀仏観によるもので、結論は同じでもよって来たる根拠は必ずしも同じとはいえないわけです。
弁栄聖者においては本仏阿弥陀如来の超越性とその霊力の衆生への内在とを縁起によって両立させる独自の仏身観、すなわち超在一神的汎神教という立場によって立つものであります。衆生(人間)の聖き心への復活(自利、救我)と、それに起因する利他行の実践(度我、聖き世嗣への道)、すなわち自利利他菩薩行への志向とその実現可能性を成立せしめる教学体系であります。弁栄聖者の実体験と自内証によって感得された体系であり、因果律の根底にまで立ち戻って導出された信仰内容であります。その故にこそ、摂取不捨万機普益を確信せしめるものがあります。
さて今一つ「弥陀章」に関してコメントしておきますと仏名の数のことです。無量寿経からとられたものの筈ですがいまの漢訳の諸本の仏名数と一致しないようです。通用の康僧鎧訳の無量寿経は異訳の中ではかなり仏名が多い部類だそうですがそれでも六十八仏、その梵本でも九十七仏だそうです。龍樹所覧の無量寿経は異本であったと考えざるをえないそうです(望月信亨『略述浄土教理史』参照)。
さて「易行品」はこの後に三十二行の長い偈をもって阿弥陀仏を称讃します。たとえば、
無量光明の慧あり、身は真金山のごとし。われいま身口意をもて合掌し、稽首し礼す。
もし人命終の時彼の国に生ずることを得ば、すなわち無量の徳を具す。この故にわれ帰命す。
人よくこの仏の無量力の功徳を念ぜば即時に必定に入る。この故にわれつねに念ず。
もし人作仏を願って心に阿弥陀を念ぜば、時に応じてために身を現じたまう。この故にわれ帰命す。
もし人善根を種うるも疑えばすなわち華開かず。信心清浄なる者は華開いてすなわち仏を見る。
人天中の最尊にして諸天頭面に礼す。七宝冠に摩尼(宝)あり。この故にわれ帰命す。
以上のような心にしみいる偈がいくつもあります。最後に引いた句に、人天中の最尊、とありますが海徳仏にも「人天中の最尊」という表現がありました。このほか寿命光明無量ともいいました。阿弥陀仏と海徳仏はどういう関係なのでしょうか。同体異名というべきなのでしょうか。
この後にも、毘婆尸仏から釈迦仏までの過去七仏に未来仏の弥勒仏をくわえた過未八仏章、徳勝仏以下の東方八仏章、三世諸仏章、諸大菩薩章が続き、それぞれ仏名、大菩薩名の列挙があってこれらに憶念、恭敬、礼拝して阿惟越致地を求むべきなり、と易行品は結ばれています。
以上が易行品の説く「信方便易行」の内容です。要するに仏力を得て初地に入る、とは具体的には阿弥陀仏の本願力を得て、というのが龍樹の主張、体験であるということでしょう。
(つづく)
根源(アルケー)に還る その2
古代ギリシァ人たちは最初は豊かな神々の世界(神話の世界)に生きていました。いわゆる多神教と称せられる世界であります。多神教における神々の豊かさはそのまま人間の精神の豊かさに連なり、たとえばその最高主神たるゼウスの神に連なることにおいて人間の威厳性が、また愛の女神アフロディティ(ローマ神ではヴィナース)に連なることにおいて美の観念が生じ発展していきました。しかしながらそのような多様性の中にあって何か一貫した統一的な「あるもの」が目覚めてゆくことになったのです。それがタレスのいうところのアルケーでした。そしてそれは万物の中にあって千変万化する各々の根源として「水」が考えられていったのです。水は固体(氷)にもなり、液体(水)にもなるし、そしてまた気体(水蒸気)ともなって万物の中に流れているからであります。しかしながら彼の弟子アナクシマンドロスAnaximandros(610~546 BC)は更に進んで「アルケーは水等の限定されたものではなく──もしそうだとすればたとえば多神教の中の一神たる水神に墜ち込んでゆきます。実際ヨーロッパのある学者たちの中にはタレスのアルケーを伝統的な水神と関連づけて説明する人たちもいました。──そのような「限定」ぺラス peras を超えた「無限定的なもの」(ト・)アペイロンto apeiron(to はギリシァ語の中性の冠詞、a は否定の語でペラスの否定として)の概念が出現してきたのです。仏教の阿弥陀 amita ──母音 i と母音 a に挟まれた t は d の発音になる、すなわちアミダ amida になる。amita はサンスクリットでそれを漢字で「阿弥陀」と当て字で表記、またミタ(mita)はペラスに、従ってアミタはアペイロンに対応、なおミタmitaは計量されたの意で、従ってアミタは無量と訳されたりもします。──のことを知らなかったアナクシマンドロスですが、彼のト・アペイロンが何と阿弥陀仏への思惟に接近していることでしょう。アナクシマンドロスも彼なりに阿弥陀仏への思惟に限りなく接近していたことが考えられます。
しかしながら紀元後になってキリスト教における排他的な一神教の成立によってギリシァ神話にみられる豊かな神々の世界は排除されてゆきました。いわば神々の殺戮が遂行せられていったのです。しかしながらキリスト教的な排他的な一神教には恐らくユダヤ民族の経験した特殊的ともいえる歴史的な背景が考えられます。そしてそのような特殊性を普遍なるものとして押しつけようとしたところにキリスト教の限界がありました。
ところでこのようなギリシァ人が追究したアルケーはどこまでも人間の必然的思惟から起ってきたものですが、仏教においてもまたそれは当然のことでした。そして弁栄聖者もまたこのアルケーに真正面から取り組まれたのでした。
万物の、また私たち一人ひとりの生起も宇宙の根本問題であります。
従来の浄土宗では、「捨此往彼 蓮華化生」(この現実の世界を捨てて(捨此)、阿弥陀仏の浄土に往生する(往彼))の方向にそのテーマは集中せられていました。上記は法然上人のお言葉ですが(『往生要集釈』)、上人の活躍された時代を考えれば、それはそれで不可避的ともいえる課題でした。
しかしながら時代も変わって近代科学の時代になって新しい課題も改めて生じてきました。すなわちそれは「私が何処から来たか」woher ich kommeの問題であります。
弁栄聖者においては私たちが帰依し、帰趣してゆく目的としての阿弥陀仏が、実はそこから私たち自らが生まれ出てくる根源(アルケー)でもあることを詳しく説かれたのでした。かくて阿弥陀仏は私たちの根源でありつつ同時に目的(テロス)であることが強調されているのであります。
ギリシァにおいてもタレスを隔たること八〇〇年も経てプロティノス(二〇四~二六九)においてそのことが気づかれていったのでした。プロティノスは『エネアデス』において「一者(ト・ヘン)においてはアルケーとテロスは同一である」と論じています。かくて万有そして私たち自身がそこから生まれ、そこへ還ってゆく一者、すなわち阿弥陀仏に目ざめていったのでした。そこでは私自身もまた万有もその中に収まり、そこに全体を包含するいわゆる体系が成立することになります。
若き山本幹夫(出家して空外)博士は恐らく弁栄聖者の思想に触発され、そして若き情熱の全体を傾けてプロティノスの研究に集中せられ、それがやがて学位論文「哲学体系構成の二途」となって世に出ることになったのです。(昭和11年)。
そのプロティノスはナイル川上流からアレキサンドリアに出て、プラトン、アリストテレスの研究に従事しました。アレキサンドリアはいうまでもなくアレキサンダー大王の名に因んで名づけられた当時のヘレニズムの中心都市であったのですが、そこにはアレキサンダー大王の哲学の師であったアリストテレスの研究所もあり、その権威ある研究所においてプロティノスもプラトン(アリストテレスの師)、アリストテレスを研究したのでした。両者はその後二千数百年にわたってヨーロッパ哲学の根幹となったのであります。
なお空外上人はプラトン、アリストテレスを深く研究され、それら両哲学者の哲学のテーマが一貫して目的としてのイデアに中心がおかれていたのに対し、それをタレス以来のアルケーと統合することにおいて、それら全体を包含する一者の体系の成立が考えられるのであります。
なおプロティノスにおいて、万物がそこから出てくるアルケーを「降り道」として、また万物がそこへ帰趣する目的すなわちテロスtelosを「昇り道」と考え、ギリシァ哲学の八百年を通して流れるその両途がプロティノスにおいて一体化され、体系化されていったところにその哲学的な深い意義が論調されているのであります。そのような哲学を新プラトン主義Neoplatonismusと称せられています。そして、それはやがてアウグスティヌス(354~430)を接点として、キリスト教世界へと流れていったのでした。(なお、そのアウグスティヌスもアフリカ出身者であることも銘記されるべきでありましょう。)かくて(新)プラトン的キリスト教がヨーロッパの中心思想となっていったのでした。
なお、空外上人はプロティノスの思想に仏教の影響のあることに言及されていますが、それはアレキサンドリアがギリシア世界と全面的に開かれ都市でありながら、また他方インド洋航路を通してインドへの開かれた交流点ともなっていた点からインド仏教との関係も大いに考えられるところであります。そのことは空外上人が、たとえばE・ベンツ(ドイツ、マールブルグ大学教授)の論文等をも引用されつつ、プロティノスの師がアンモニオス・サッカスであり、サッカスが釈尊の釈との関連性が論じられたりしている点からも興味がひかれるところです。プロティノスはやがてペルシア遠征のゴルデイアヌス(ローマ皇帝)の軍に従ってインドへの旅を試みたのですが、皇帝の暗殺によって果たせず、その後アレキサンドリアからローマに移ってそこで終生哲学活動に従事し、不朽の精神的成果を残すことになったのでした。プロティノスにおける万有の流出と還帰というプラトン、アリストテレスにも実現できなかった体系的思惟はインド仏教の思惟の影響下で成立したことも考えられます。なお、フランスのプロティノス研究者たちもかかる視点から考えているようです。
なおアウグスティヌスは『告白』という彼の自省録において、「もし私が新プラトン主義(プロティノス)を知らなかったならば、これほど深くキリスト教を理解することはできなかったであろう」と述べていますが、そのことは又キリスト教がプロティノスの哲学と接して深められていったことも考えられます。
なお「告白」とは、『如来光明礼拝儀』(至心に懺悔す)における、
法身と智慧と解脱の三徳を備え給う如来に告白し奉る…
にもみられる言葉ですが、この用語は本来、キリスト教の専門用語です。(『礼拝儀』はキリスト教的用語がその多くを占めています。「告白」confessionとは、たとえば『キリスト教大辞典』(教文館)では、「神に対する自己の信仰を、明白な言葉をもっていい表わすこと」と定義されているように、もっぱら神に向かっての対話がその内容であります。アウグスティヌスの『告白』も全卷を貫いて神に対して決して三人称(神)ではなく二人称で、すなわち「あなた(汝)」と呼びかけつつ語られています。たとえばその著書の冒頭における、
あなた(汝=神)は私をあなたに向けてお創りになりました。それ故に私はあなた(汝)のみ許に休らうまでは休らうことはありません。
の文は神による私の創造と神への帰入が「あなた」でまとめて述べられているのであります。この言葉でヨーロッパ世界は完結したといえます。
その点では弁栄聖者も同様で、私たちがそこから出てくる本体を法身として、そして私たちがそこへと還ってゆく面を報身の如来として説かれたのでした。
(つづく)
弁栄聖者の俤(おもかげ)32
◇〈弁栄聖者ご法話〉聞き書き その二(授戒会の説教)〈つづき〉
▽第四、酤酒戒 (筆記なし。)
飲酒は軽き罪なれども、酤酒、即ち酒を売りて、人に飲ましむるは罪重し。菩薩は利他を本とす。他の心を迷わすは、自ら飲んで迷う罪に過ぎたればなり。
▽第五、妄語戒
正見とは正しき見込み即ち真理を見る目である。正見により、正しき生活ができる。この戒は人生を徒らに過ごしてはならぬ事を戒める。動物的生活を戒むる戒である。
何事も皆いつわりの世の中に
死ぬる一つはまことなりけり
▽第六、説四衆過戒
人の悪口をいってはならぬが、殊に仏法に帰依した人の事を悪くいうのは、重い罪である。
▽第七、自讃毀他戒
自分をほめてはならぬ。うぬぼれは悪い。人が何と悪口をいうとも、忍んで受けるのが菩薩である。自分の悪いのに気が付けば、速に改めよ。人にほめられても喜ぶ勿れ。自分を毀る人あらば、わがために良い師匠だと思え。他人が毀られているのを見れば、その毀りを自分が引き受け、良い事を人に譲るのが仏子の務めである。
▽第八、慳貪不与戒
人に物を施す時は、良い心持ちでせよ。喜んで施せ。何でも求められる物は施せ。施しに三通りある。財施、法施、無畏施の三つである。財施して、人に善心を起させると法施ともなる。無畏施は災難、苦労、悩みなどを無くしてやる事である。
▽第九、瞋不受悔戒
人を怒らせてはならぬ。慈悲心を養え。腹が立っても人が赦してくれと頼めば、〈受け〉容れてやれ。それを受け容れぬと重い罪になる。人にはプンと怒る性分が有る。それは、しかたがない。其の怒りを持ち続けて解けぬ時は、重い罪になる。
慈悲の眼に憎しと思う人はなし
罪ある人ぞ哀れなりける
▽第十、邪見謗法戒
邪見を起して、正法を謗るは、重い罪である。
お布施のこころ(その3)
そのお電話が終わりしばらくたったある日、その夫婦から連絡があり、改めて結婚式をすることになりました。
そこで、天国のお父さんにも空から見ていただきたいということで、建物の中ではなく、きれいなお庭で行うことになりました。しかし、当日はあいにくの雨です。準備をしている有賀さんのそばで、夫婦は暗い顔をしています。
「どうか晴れますように。」
と有賀さんは真剣に祈っていました。
するとどうでしょう。予定の十五分前に雨はピタリとやみ、式は無事お庭で執り行うことができたのです。
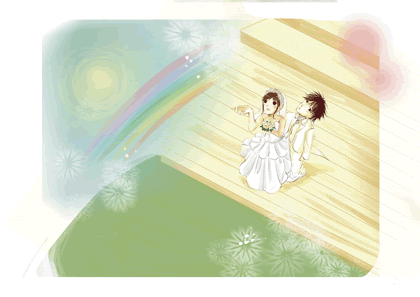
有賀さんはその夫婦に、
「奇跡がおきましたね!」
そうお声がけしたとき、夫婦からかえってきた言葉に有賀さんは涙しました。
「いえ、私たちにとっての奇跡は有賀さんに出会えたことです」
その後、有賀さんは仕事で不安なとき、つらいとき、この言葉を思い出して、有賀さんは今もその仕事をつづけています。
この夫婦に喜んでもらおうというやさしい気持ちも、お布施のこころ。
そして、有賀さんの人生をずっとささえているこの夫婦の美しい言葉もお布施のこころ。
みんなも、
「あなたに出会えてよかった!」
そうたくさん言ってもらえる、お布施のこころをもった立派な人になってね。
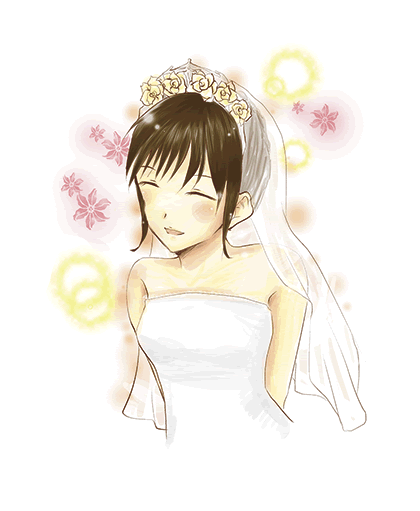
(おしまい)
イラスト:藤富千尋
ひかり2013年07月号


弁栄聖者 今月の御道詠
ききもせぬ 見もせぬ日より 恋しける
鹿野のそのうに 鳴く鹿の声仏蹟参拝 鹿野苑『日本の光』
05 光明会各会所年間行事
06 聖者の俤(おもかげ)其三十一 中井 常次郎
08 根源(アルケー)に還る その1 河波 定昌
11 感動説話「名体不離」 明千山人
12 子供といっしょに学びましょう 41
14 光明主義と今を生きる女性 内藤 規利子
16 光り輝く淨土への道74 山上 光俊
20 能生法話「穢(けが)す」 辻本 光信
21 特別会員及び賛助会員のお願い
22 お袖をつかんで 吉水 岳彦
「第十四歩 わがことと喜ぶ」
24 仏力と易行ということ その2 佐々木 有一
28 ひかりの輪 光明学園 「1学年宿泊研修」
33 第39回「法のつどい」報告
36 聖者の霊筆 その9
38 写仏のすすめ
40 支部だより
40 第92回唐沢山別時念仏会ご案内
41 第13回 相模原親子別時念仏会ご案内
42 大阪府 豊中市 徳林院「光のつどい」ご案内
42 近畿支部夏期別時念仏会のご案内
44 財団レポート清納報告
46 清納報告
47 新刊本の御案内・こちらひかり編集室
根源(アルケー)に還る その1
今回は1「根源に還る」のテーマでお話させていただきます。ここで根源とは万物の根源のことですが、また、同時に何よりも私自身にとっての根源でもあります。すなわち、私自身がそこから生まれ出た根源であります。
そのことを最初に問うたのはギリシアの哲学者タレス Thalēs(紀元前624、あるいは640~546)でした。それによってギリシアの思想は一変しました。そしてその根源(もとのもの、また始源ともいわれます)はアルケー archē とよばれていました。
このような万物、また私自身について考える場合、必然的にかかるアルケーへの思想が起こってきます。それまで雑然としていた考え方が、かかるアルケーによって宇宙を統一的に考えられるようになってゆくからです。このような思考を開始したのがタレスでした。
このような根源への問いには東洋も西洋もありません。私たち日本人もまたギリシア人たちと同じ立場に立っているのであり、どこまでも普遍的であります。
その同じ問題は弘法大師空海(774-835)においても発せられていました。弘法大師とタレスの間には1200年以上もの年代の差がありますが、その根源への問い、すなわち根源的な問いに変わるところはありません。弘法大師は『秘蔵宝鑰』)(鑰は鍵の意、如来の秘密の世界に入る宝の鑰の意)という書の中で、
生まれ生まれ生まれ生まれて、
生の始めに暗く、
死に死に死に死んで、
死の終りに冥し。
(『弘法大師著作全集』第1巻125頁)
と述べています。その背景には輪廻の思想があってのことでしょう。生まれるについても一回だけのことでなく、何度生まれてきても生まれてきたその生の始め、すなわちアルケーに暗く、また同様に何度死んでも死の終りに冥し、と云っているのであります。すなわち、未来永劫にわたって流転三界し、生の始まりに暗く、また死にゆく未来にも暗いことが述べられているのであります。それはまさに私自身にとっての生死の問題そのものであります。
かかる生死の問題には、西洋も東洋もなく、また過去も現在もありません。
二十世紀を代表するドイツの哲学者カール・ヤスパースKarl Jaspers(1883-1969)の比較的晩年に著した彼の宗教哲学の集大成ともいえる『啓示に対する哲学的信仰』という著書の結論的な部分で、
私がどこからwoherきたかということを私は知らない。
また、
私がどこへwohinゆくのかということも知らない。
と。すなわちヤスパースも弘法大師と同じ問いを発しているのであります。
そのことはまたヤスパースと並んで20世紀の最大の哲学者であったマルティン・ハイデッガーMartin Heidegger (1889-1976)もその同じ問題と対決しています。彼は『思惟とは何か』という著書の中で、思惟の根源性を問うているのですが、そこではもはや私が何を考えているか(すなわちcogito ─ デカルトの言葉)の次元を超えて、限りなくその思惟が深められてゆきます。この著書の名、すなわち『思惟とは何か』の原文は《Was heißt Denken?》であり、「何 was が私を呼んでいるのか」であります。それはたとえば私たちが念仏する時、勝手に(主観的に)念仏しているのではなく、阿弥陀仏から喚びかけられて、それが私たち一人ひとりの念仏になっているように、思惟も存在 Sein そのものによって喚びかけられて生起していることを意味しています。それはまさに縁起そのものであります。そこには近代ヨーロッパ人の抜き難い前提たる主観主義Subjektivismus(あるいは自我中心主義)からの脱却が遂行せられているのであります。そしてハイデッガーはその著の中で、もはや科学や従来の哲学を超えて一つの根底(あるいは基盤)につき当っているというのであります。その根底とは「私たちがそこから生まれ、そこへと死んでゆく基盤」と云っています。そして気がつけば私たち(すなわち西洋人たち)も実に最初からその基盤と相い対していた、と云っているのであります。まさにこのようにヨーロッパの最先端の哲学も生死の根源に立ち向かっているのであります。
ところで本題「根源に還る」において、私たちがそこから出て来た根源へ「還る」ことにおいて、その根源はそこへ向かってゆく目的(標)ともなります。そして根源が同時に目的(標)となる時、すなわち根源が目的と同一のものであると気づいた時、タレス以来のギリシア哲学は完結することになります。そしてそれを実現したのがプロティノPlotinos(204-269)でした。彼には弟子のポルピュリオスの筆記録である『エネアデス』Ennéades があり、その中で根源が目的 telos であると断ずることによってタレス以来、800年にわたるギリシア哲学は完結していったのであります。
なお山本空外上人の業績は難解なギリシア語で書かれた『エネアデス』を丹念に読まれて、それを『哲学体系構成の二途』としてまとめられたのでした。それが東京大学に提出した学位論文となったのです。そしてそのプロティノスの哲学が更にキリスト教と結びついて現在に至るまでのヨーロッパ文明の基幹となったのでした。
ところでこの生まれた処(根源)が目的(すなわち帰趣)であるとする点で、故郷 Heimat あるいは「還る」という思想が成り立ちます。この「還る」という思想の喪失 Heimatlosigkeit は現在の根本的な病いともいえるもので、たとえばハイデッガーもその点で警鐘を鳴らしています。
すなわち彼は1959年、彼の生まれ故郷である南ドイツのメスキルヒという町で、その町長に招かれてGelassenheit(「放下」の題で邦訳されています)のタイトルで公開講演を行っているのですが、ここで彼は、
水素爆弾の危機が去った時、私たちはそれよりも更に恐るべき危機に直面することになる。すなわちそれは私たちが還ってゆく心の故郷(大地)を失っているということである。
と述べているのです。
東洋でも西洋でも、おしなべて「還る」という思想、すなわちそこからでてきたそこへ還るという円環的な思惟が消滅してしまっているということにもなるでしょう。ハイデッカーは科学的な計量的な思惟によって故郷への思惟が消滅してしまっていることを批判しているのであります。あるいはまたダーウィンの進化論やマルクスの唯物史観に見られるような直線的な歴史観もその原因になっているとも云えます。
田中木叉上人もこのような還る処のない迷盲の凡夫を「三界の宿無し犬」と云われていたこともあります。世にアナーキスト anarchist といわれる人たちにも、みずからの出来するアルケーなくしては考えられないにもかかわらず、アルケーがないa(n)arche(最初のaは否定の言葉)と称しているのですが、自己矛盾という他はありません。おしなべて彼らも結果的に生命の不安におののいてゆくのであります。
法然上人にとってもお浄土の世界は単なる「捨此往彼)」といわれるように、ただ往生してゆくだけの彼処ではなく、むしろそこに還ってゆく本来の故郷に他なりませんでした。そのことは法然上人の最も確実な資料とされる『醍醐本法然上人伝記』の中の「御臨終日記」の中の次のような一文、すなわち、
…看病の人の中にひとりの僧ありて、問いたてまつりて申すよう。極楽へは往生したまふべしやと申しければ、答えてのたまわく、われもと極楽にありし身なれば、さこそはあらんずらめとのたまひけり。
(『昭和新脩法然上人全集』871頁)
と述べられていることが記されています。
私たちがそこから生まれ出た根源アルケーが、同時にそこへ還ってゆく目的(テロス)と云ったプロティノスの「一者」to hen こそ実にそこから生まれ、そこへと還ってゆく阿弥陀仏に他なりません。空外上人の著作、『一者と阿弥陀』とはまさにその内容に他なりませんでした。かかるプロティノスの哲学はいわゆる新プラトン主義、あるいはプラトン主義 Platonism として西洋文化の根幹となっていったのですが、そのプロティノスの一者がそのまま阿弥陀仏と一つのものでした。かくて空外上人において東西を包含する阿弥陀仏(一者)の体系が開かれていったのであります。
(つづく)
- 本稿は平成25五年5月19日、京都百万遍知恩寺の「法のつどい」における講述に一部分加筆した内容です。 [↩]
仏力と易行ということ ─無礙光の序説として─ その2
関東支部会員 佐々木 有一
二、菩薩の難行
龍樹がまず何よりも重視するのは菩薩の道を歩むということであります。声聞や縁覚も煩悩をはなれた聖者でありますが、龍樹は彼らは生死の海をみずから渡るだけであり、大事なことは他者をも渡すということである、それには十地の境地に入らなければならないと強調します。ここで菩薩と声聞・縁覚は共に涅槃に入るけれども両者の違いについて、龍樹は次の二点を指摘します(「序品」)。声聞や縁覚は「禅定障」と「一切法障」から離れられず、菩薩が仏になれるのはこれを離れることができるからだというのです。この差異はことばに言い尽くせないほど大きいといいます。禅定障とは禅定を保ったり静寂にいることにこだわり、おろかな人と関わったり街中に出ることを好まず、紛争にも近づかないという態度です。一切法障は一切の人や事柄に対し好き嫌いの差別心を捨てきれないことであります。
また同じ「序品」で菩薩には「堅心」があるが堅心と反対の「軟心」の者は声聞・縁覚の二乗に堕すのだといいます。軟心とは、自分はどうして久しく生死輪廻のただ中にあって多くの苦悩を受ける必要があろうか、速やかにみずからの苦を滅して涅槃に入りたい、と思う心です。堅心は自分一人のために涅槃に入ることを求めず、利他の修行のためとあれば生死の世界にとどまることをいとわず恐れない心であります。
華厳経は仏教信者の修行の階位として十信、十住、十行、十回向、十地という長い道のりを立て、究極的には等覚(これから妙覚の仏果を得ようとする位、一生補処、弥勒菩薩がその一例)、妙覚という仏になるというのです(五十二位説)。この十地からが菩薩といわれる階位です。十回向の最後の修行で無分別智が開け、また後得智も開けて十地の最初、初地とも歓喜地ともいわれる境位に上ります。この境位は修道論のうえでは見道とも通達位とも呼ばれ、梵語では不退転地という意味の阿惟越致地といいます。『十住毘婆沙論』ではこの用語が多く使われますが小稿ではできるだけ初地という言葉で進めたいと思います。
ここで少し用語の整理をしておきます。まず菩薩とは菩提薩埵の略で菩提は仏の正覚の智慧、さとり、の意味、薩埵は人々ですから覚りを求めて修行する人、が原義です。もとは十地に上った聖者のことでしたが次第に「凡夫の菩薩」という言葉も生まれます。菩提心を発しさえすればもうそれは菩薩だという考え方です。他者のことを強く意識するのが大乗仏教の大乗たる所以ですからこのような語義の拡大は自然でしょう。「仏になることをめざすのは、他者の力になりたいという思いを実現するためです。菩薩すなわち菩提薩埵の語は、後に、菩提を求める人というより、菩提(覚り)と薩埵(人々)の双方を心にかける人の意と解されていくようになるのでした。」(竹村牧男『般若心経を読みとく』)
次に、『十住毘婆沙論』で十住というのは十地経の十地を鳩摩羅什(344~413または350~409)が十住と訳したからです。十地経は龍樹以前の1~2世紀頃に成立したと考えられ、後に(おそらく4世紀頃に)集大成された華厳経に「十地品」という品名で編入されました。華厳経(六十巻本)は仏駄跋陀羅(359~429)が漢訳したもので、その「十住品」に説くものが先にあげた修行の階位としての十住位です。信が固まったときに初発心住に住するというわけです。
ところで華厳思想の大きな特徴は相即相入にありといわれます。華厳教学の縁起思想のことで、拙稿「自他不二への向上み」で多少筋道を立てて解説を試みていますが、いまごく簡潔にいいますなら、相即とは一と多との関係を述べたもので、一があってこそ多が成り立ち、また多によって一が考えられるので、一と多とは密接不離であるということです。相入とは一におけるはたらきは全体のはたらきに影響し、全体のはたらきから当然一のはたらきが考えられるから、これもまた、密接不離であるということになります。体(そのもの)の方面であらゆる物が一つであるというのが相即、用(はたらき)の方面であらゆる物が一つだというのが相入です。人間の我でも法(存在)でも縁起によって現象があると考えますから、ものの実体は否認され、あらゆるものが網の目のように互いに入り合っています。具体的個体の存在とはたらきとは、そのまま全体における存在とはたらきになるという世界観です。円融、融通、融即ともいわれます(主として中村元『仏教語大辞典』)。
この相即相入の考え方は空間的にばかりでなく時間的にも適用されると考えられています。一例として菩提心を発して十住の最初、初発心住の位に至れば、その後に越えて行く初発心住以後の十住、十行、十回向、十地など他の諸々の階位を悉く摂する意味を持つことになりますから「初発心時便成正覚」(初発心の時、すなわち正覚を成ず)と主張されます。これは「住」の前の「信」の方からみれば「信満成仏」ともいわれ、共に華厳思想の特徴的な成句として有名です。
さていずれにしても十地に入る、菩薩になるということは大変なことで、十信から十回向という四十の修行の位を履み終えてある種の完成に近づいたというところです。人間の思いを超えた智慧の世界に入ることであり、この智慧の故にこそ慈悲、大悲の心が湧き上がって利他に生きる菩薩の道を歩むわけです。智慧を求め慈悲に生きる菩薩の道は一番最初は菩提心によって始まります。菩提心はいかにして生まれるのか、いかにして発すのか、それが最初のテーマになります。
龍樹は菩提心が発るには七つの因縁があるといいます(「発菩提心品」)。
一には、如来が衆生に発心をおこさせる、
二には、仏法の崩壊をみてこれを守護しようとしておこす、
三には、苦悩の人々を見て大悲をおこして発心する、
四には、菩薩の教導によって発心する、
五には、菩薩の行業を見てそのようになりたいと願っておこす、
六には、自ら仏や僧に布施することによりそれが縁となって発心する、
七には、仏身の相貌を見て歓喜して発心する。1
しかもこの七つの因縁のうち、初めの三つの因縁によっておこった発心は途中でくじけることはなく必ず成就するが、他の四つの発心は必ずしも成就しない、といいます(「調伏心品」)。そのわけはどういうことでしょうか。この後に説明が続きますが、いかにもインド的な、分析と例示(列挙?)が次々と提示されていきます。こうしたいささか思弁的とさえ思わせるほどの分析例示が他の箇所にも同様のスタイルで続きます。余談ですが、国連など国際会議の場でよく耳にする「インド人を黙らせることは日本人を喋らせることよりもはるかに難しい」というジョークを思い出します。
龍樹はまず次の四つが菩提心を失わせる原因になるといいます。(細川氏訳抄録)
まず、法を敬重せず、ということです。仏法を恭敬し、尊重し、稀有であると喜ぶ心がなくなると菩提心が失われます。
次は、憍慢心で、まだ身についていないものを身についたと思い、わかっていないものをもうわかったと思うその心です。憍慢が菩提心を失わせます。
三には、妄語無実で、妄語には軽も重もあるものの実語でなく、人を欺き、それが重なると菩提心が失われます。
四には、善知識を尊敬しないこと。善知識(指導者)に対し、はじめは尊敬の念をもっていたものが、だんだんとなれてくるとこの心を失い、菩提心も失われていくのです。
この四つの外にまだあるか、との問いに対して、
最要の法を惜しんで与えないもの、小乗の楽しみを貪るもの、菩薩を誹謗するもの、求道者を軽賤するもの、これもまた同様である。
と答えます。最要の法を惜しむとは、得がたい深い法義を自分は知っており、それは人々のためになるものであるのに、これを教えるとその人が自分に並ぶようになることを怖れて惜しみ隠して教えないことをいいます。さらに、
善知識に対し、心に恨みを抱き、また反対に諂と曲の心(こびへつらい)があるもの、及び利養(財産、名声など)を貪るものも同様である。
と続きます。
すごいのはこの後にまだ次のような「魔事」をつぎつぎと例示(列挙?)して菩提心の挫け、消失を戒めていることです。これも「調伏心品」に出ていますが、現代語訳は細川氏のものを借用(一部は抄録)しています。
また諸々の魔事をさとらず、菩提心劣弱(煩悩が強い)であること、及び業障(人を求道から逆転させるようなはたらき)と法障(不善の教えを喜び真実の教法への思いが浅い)、これらの四つもまた菩提心を失わせる。
これらは鈍根懈慢の者の通弊であります。
さて魔事とはどのようなことでしょうか。
仏の教説が説かれるとき、はやくそれを喜べないでありがたく頂戴するまでによほど時間がかかること、これが魔事である(不疾楽説)。
喜んで説法を聞いているとき、いろいろのことがおこってきて聞法を妨げられること、これも魔事である(余縁散乱)。
書物を読んだり説法を聞いたりしているとき、心が散乱して集中できない、これも魔事である(其心散乱)。
説法のときほかのことを連想してそのことに心が引っぱられたり思わずしのび笑いをしたりする、これも魔事である。
お互いに話し合うとき、議論になってしまって両方の意見が対立し、本当のわけがらが通じないようになる、これも魔事である。
説法の座で、自分には関係がない、聞きたくないなどという心がおこってとうとう帰ってしまう、これも魔事である。
聞法のとき、説法の中に政冶、戦争、経済、愛憎、父母兄弟その他の男性のこと女性のこと、着物、食物、薬のことなどが説かれると、それによって心が散乱したり、またそれに喜んで仏法の心を失ってしまう、これも魔事である。
説法の中で地獄の諸苦を説くとき、このような苦しみを早くすべて尽くして浄土に往生することがわが身の利益であると説く人がいたり、あるいは世間での金儲け、立身出世、その他の幸福を称賛し、そのようなものを手に入れるのが大利を得ることだと説く人がいるが、これらはいずれも魔が説教者に化けているのであって、これらの内容ことごとくが魔事である。
このように一切の善法に対して障害となるものを、すべて魔事というのである。
さていかがですか。いささかうんざりですがやはり胸に手を当てて時に反省懺悔せざるをえないものがありそうです。
さて菩提心を発してそれを持続していくのは以上のように並大抵のことではありませんが、それはそもそも初地に入るための修行がそれほどに至難なことであるからです。後の「易行品」の表現を借りれば「勤行精進」の道の困難さであります。龍樹はつぎの八法を具しおわって初めて初地に至るといいます(「入初地品」)。すなわち、
厚く善根(貪恚癡の三毒のないこと)を種え、
善く諸行を行じ(持戒)、
善く諸々の資用(仏道のための補助、ここでは他の七法のこと)を集め、
善く諸仏を供養(法を聴聞、華香を奉献、礼侍など)し、
善知識(大乗の指導者)に護られ、
深心(二種深信に開く深心ではなく、大願を発し必定地に入らんとねがう心を初地の深心の相という)を具足し、
悲心(衆生を憐れみ苦難を救済する心)あって衆生を念じ、
無上の法を信解す。
この八法を具しおわってまさにみずから発願して言うべし。
われみずから度することを得おわって、まさに衆生を度すべし、と。
発願こそ仏道のアルファであり、自利利他の願にほかならず、十地の根本というわけです。
すべての行者がこのような八法を履み行って勤行精進が進めばいいのですが、なかなかそうはまいりません。八法とは要するに「戒定慧の三学」のこととみていいのではないかと思います。
龍樹は「序品」のところですでにこう云っています(細川氏訳抄録)。
福徳すぐれ、能力があってこの十地経を聞いただけで深いわけがらを理解するような人たちには解釈の必要がない。私はこの人のためにこの論をつくるのではない。福徳すぐれ、能力のある人とは、仏語を聞いてよくみずから理解できる人のことをいう。ちょうど健康な大人はどんな苦い薬もそのまま飲み込むことができるが、子供には蜜で調合しないとこの薬は飲めない。このような福徳すぐれた人を仏教では善人という。善人は信、精進、念、定を具え、身口意の三業に善を保ち、無貪、無恚、無癡の存在である。私はこのような善人を対象としていない。鈍根懈慢の者に説くのである。この人たちは経を読んでも自分の力では理解できない。文が長く、難解な文字が多く、内容がわかりにくく説明がよくわからず、何回よんでも理解できない。この人たちのために、毘婆沙をつくり経の長い文を簡略にし、読みやすい文字にかえ、譬えや例をひいて内容をわかりやすくし、歌やまとめを出してこの人たちの理解を助けたい。そのためにこの論をつくるのである。
かように本論『十住毘婆娑論』の造論の趣旨が明かされておりました。
そういえば法華経にもたしか「三周説法」ということがありました。釈尊は三度同じことを繰りかえして説かれるということで、まず法の内容を理論的に説き(「法説周」)、次いで巧みな譬喩を用いて説き(「譬説周」)、それでもまだ仏の本意(法)を会得できない場合には過去の事実を例に挙げてお説きになります(「因縁周」)。このように三周りに懇切丁寧にお説きになりますので三周説法といい、仏の慈悲の大きさをあらためて感じることになるわけです。龍樹も同様の慈悲心にたって『十住毘婆沙論』を著わしたことになります。
さて入初地をめざして修行に入ることになりますが、人々の多くは不退転に達しないまま行きつ戻りつするわけです。この人たちを龍樹は「敗壊の菩薩」と「漸漸精進の菩薩」の二つにわけます(「阿惟越致相品」)。前者はこのままではもはやどうにもならない者、後者は時間がかかりながらもだんだんと精進がすすんでいずれは初地に至る者です。この両者をともに一括して「惟越致の菩薩」とくくっていますが、「敗壊」から「漸漸」へ、やがては「阿惟越致」の菩薩へと導くものがいわゆる「易行品」の教えであります。鈍根懈慢の人を対象としてこの論を造るとは、実は絶対多数の衆生を対象としてこの論を造ることと同じですから、だからこそ万機普益への道に通ずるのだといえるわけです。惟越致の菩薩はたとえ外の姿は菩薩行を行じているようでも内面は菩薩としての内容をもたない求道者であります。不退転でなく退転しているわけですが、苦しみ退転している実相が、実は仏力をいただく資用、材料となるわけです。仏の大悲の故に、であります。敗壊の菩薩、漸漸精進の菩薩が仏に出会い、仏の仏力をいただいていく次第が「易行品」で明かされていきます。
(つづく)
- この現代語訳は細川巌『龍樹の仏教―十住毘婆沙論』によっています。細川巌氏(1919~1996)は広島文理科大学化学科卒、福岡教育大学名誉教授、親鸞に帰依し大学でも仏教研究会をつくり仏教の普及研究に尽くされた。以下にも注記しながら引用することがあります。 [↩]
弁栄聖者の俤(おもかげ)31
◇〈弁栄聖者ご法話〉聞き書き その二(授戒会の説教)〈つづき〉
▽第一、快意殺生戒
かわい〈可愛い〉とかわいそうとはちがう。鶏は子を愛するが、病める子を哀れむ事を知らぬ。然るに、人間にはかわいそうという心がある。殺生を重ねると、このかわいそうという心が消える。仁を殺す事になる。仁を殺せば人間の資格が無くなる。人間は頭を天に向けて立っている。畜生は皆体を横たえて歩む。人間には理性あれど、畜生には無い。邪見な者の頭は下に向いている。
殺生の中で、虫や魚を殺すよりも、人間を殺すは罪が重い。人の中でも、君を殺し、父母を殺し、覚者を殺すのは、更に罪が重い。最も重い罪は、己が仏性を殺す事である。即ち成仏せぬのが最も大きな罪である。なぜかといえば、釈尊がこの世に出られたのも、吾々を成仏させんが為めであり、過去の聖者達の御苦労も吾々を化導せんがためであり、その上、吾々は毎日多くの殺生をして生きている事を思えば、是等の御苦労や犠牲を無駄にしてはならぬからである。吾々は仏性を育てるために生かされている事を知らねばならぬ。
戒を受けたならば発得せよ。もし発得せねば結縁に止まる。われらは元より仏の子であるが、それを知らなかった。このたび戒を受けて、仏子の自覚を得た。菩薩の仲間入りをしたのであるから、今までと異なって、一切の衆生は兄弟であると心得ねばならぬ。この心を承知したのが発得である。菩薩の心を起こせば、心霊の飾、即ち瓔珞ができたのである。この瓔珞は、お金で買えない。人格に相応したものである。如来光明歎徳章に「この光に遇う者は、心の三つの汚れ消え失せて、身も心も柔らかに、悦び充ちて善き心起らん」とあるは、心を飾る瓔珞が立派になる事を示されたものである。
念仏を申せば、如来に同化され、一切の罪が消される。一心に念仏せば、仏念いの心が起り、如来の感化を蒙る。
殺生戒は生物に限らず、機械、器具の如き物までも生かして使う事である。水でも無駄使いをしてはならぬ。
いたづらに枕を照らすともし火も
思えば人のあぶらなりけり
時間を殺す人は、つまらぬ人間になる。
▽第二、不与取戒 盗みを戒む。
盗みに色々ある。従って其の業もまちまちである。人間に悪い事をさせぬように、はずかしいという心が与えられている。
伝灯相承というは、釈迦如来から今日まで、代々教えを受けつぐ事。自誓持戒というは、一心に七日、十日、一月、一年と仏に祈り、懺悔し、仏の現れを待って戒を授かる事である。
▽第三、不邪淫戒 家庭を戒む。
小乗戒は外形に止まるが、大乗戒は内面即ち心を浄くするにある。この戒は、仏心を呼び起して、道ならぬ動物心を制するのである。人は正しい縁に因って結婚するけれども、他の動物は、そうで無い。夫婦は家庭に於て観音、勢至の役をつとめねばならぬ。
五倫〈儒教の教え。人間関係を規律する五つの徳目。君臣の義、父子の親、夫婦の別、長幼の序、朋友の信の五つ〉のうちで、夫婦は道の元である。夫婦は互に礼儀が無くてはならぬ。この道を君に用うれば、忠となり、親に対せば孝となる。畜生には、夫婦の間に礼儀が無い。
釈尊は葬式の引導をなさらなかったが、結婚の仲立をされた事がしばしばある。世尊が結婚式に臨み、新婚者を戒められて仰せられるに、
汝等結婚に先立ちて、まず真理と結婚せよ。真理は永遠に変わるものにあらざれば、真理に因って結ばれたる夫婦は、永遠に離れる事が無い
と。然るに、人は多く結婚前には相手の良い方のみを見、夫婦となって後は、悪い方を見る。即ち外面的結婚であるから、結果が悪い。精神的結婚でなければならぬ。姿や財産で結ばれた夫婦は、外面的変化と共に愛も変わる。
南無即ち帰命の帰は、とつぐ事である。己が全生命を捧げて、如来と結婚する事である。如来の両手なる観音、勢至の如き夫婦とならねばならぬ。
(つづく)
