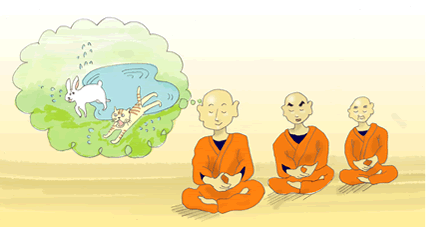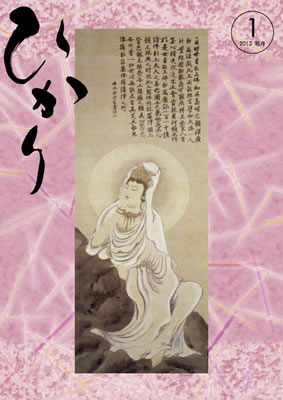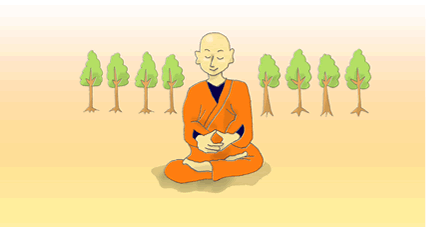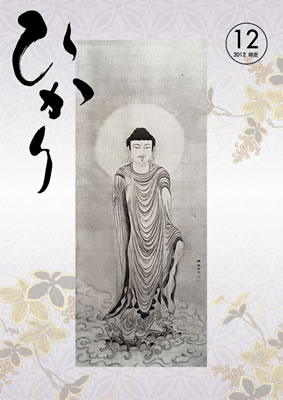念声是一について
光明修養会上首 河波 定昌
さきに「名体不離」について述べました。すなわち阿弥陀仏の名号と阿弥陀仏ご自身の三身四智等の一切の功徳等の内容とが一体であるとのことを述べました。そしてそれを展開されたのが法然上人でした。
そしてそこから必然的に「念声是一」の論が展開されてゆくのであります。すなわち心に阿弥陀仏を念ずることと阿弥陀仏の名を声に出してとなえることは同一であるということであります。そしてまさにそのことによって老若男女等、一切の凡夫や衆生たちにも仏道実践が可能となり、悟りに連なってゆくことができるのであります。
そこには法然上人における宗教的実践の一大飛躍が考えられます。
すなわち法然上人において、具体的には阿弥陀仏の四十八願の中の第十八願に「乃至十念」とある念と、善導大師の『観念法門』『往生礼讃』に示されている「下至十声」の声とはその意味において同一である、という点においてであります。念称是一とも念声是一ともいわれます。これは法然上人の『選択本願念仏集』(第三章)に述べられている言葉で、その文に、
問うていわく、『経』(無量寿経)に十念と云い、『釈』に十声と云う。念声の義いかん。答えていわく、念声は是れ一なり、何を以てか知ることを得たる。『観経』の下品下生にいわく、「声をして絶えざらしめ十念を具足して南無阿弥陀仏と称せしむ、仏名を称するが故に念々の中において八十億劫の生死の罪を除く」と。今この文によるに声はこれ念なり、念は即ちこれ声なること、その意明らけし……故に知りぬ、念は即ちこれ唱なり。
と示されています。
このようにして法然仏教は称・声・唱の一点に集中せられていったのであります。そしてまさにその点でこの教えが一切衆生に平等に開かれ(一切衆生平等往生)、しかも万徳とあらゆる悟りの内容がその中に実現せられてゆくのであります。まさにその点で法然仏教のそれまでの仏教の諸宗派に対する独立宣言の意味があります。弁栄聖者の光明主義もその線上において十二光仏の体系として展開せられていったのであります。
そしてたとえ私たち凡夫の一声一念であっても、そこに阿弥陀仏の一切の悟りの内容(万徳)が入ってくるという点ではこの稿の第二の「超越と内在のダイナミズム」において述べたところですが、同じような論理の展開がキリスト教においてもみられるところに興味深いものがあります。たとえば二十世紀のドイツで最大のカトリックの神学者にカール・ラーナー Karl Rahner (1904-1984)等において。また元照律師(宋の時代の人 1048-1116)の著書『仏説阿弥陀経義疏』巻下(『浄全』五、六八五下)の中の文、すなわち、
問う。四字(阿弥陀仏)の名号は凡下つねに聞く、何の勝能ありてか衆善に超過せるや。答えて、仏身は相にあらず、果徳の深高なり。嘉名を立てずば妙体をあらわすことなし。十方三世の諸仏みな異名あり。いわんやわが弥陀の名をもって物(衆生)を摂す。これをもって耳に聞き、口に誦すれば、無辺の聖徳は識心に攬入し、長く仏種となりて、とみに億劫の重罪を除き、無上菩提を獲証せん。
の文が見られます。
このように称名における超越者の衆生への突入がこの文では「攬入」と述べられていますが、「攬入」とは集中して入ってくることを意味しています。
なお超越者の衆生心中への突入は『観無量寿経』では「入」(サンスクリットでは avatāra)ですが、それはキリスト教における祈りにおいても共通しており、たとえばマイスター・エックハルト(1260-1327)は突入を「突破」 durchbrechen として論じています。それは法然上人の「月かげの歌」における「すむ」とどこまでも対応していることが考えられます。そしてその「すむ」には先述のカール・ラーナーにおける「自己贈与」の思想ともかかわっていることが考えられます。
このように大乗仏教においても、またキリスト教においても、その祈り(三昧)における共通した地平の開けをみることができるでしょう。その称名に即しての「入」ないし突破には煩悩に閉ざされていた自分がその罪業から解放されてゆく契機に他なりません。その典型的な例として、「利剣の名号」がみられます。すなわち善導大師の『般舟讃』に、
門々は不同にして八万四(千)なるは、無明と果と業因とを滅せんがためなり。利剣は即ち是れ弥陀の(名)号なり、一声称念すれば罪皆除く
と述べられています。すなわち阿弥陀仏の名号がよく一切の煩悩罪障を断除することは、ちょうど利剣がよく物を断つのに似ているので、「利剣の名号」ということが示されているのであります。
また田中木叉上人の「じひの華つみうた」の中にも、
火の中に 蓮や生ぜん 奮迅の
南無の一声 乾坤を割く
の歌がみられます。堕地獄の炎の中にあって「南無」の一声で新しい救いの新天地が開けてゆく旨が説かれています。
阿弥陀仏の名号は何にもまして煩悩の中にある凡夫にとって救いの手だてとなります。
道元禅師(1200-1253)も若年の頃は念仏称名を「田の蛙の鳴くが如し」と否定的に論じられたりもしていましたが、次第に老齢となり、体力も衰退してゆく状況の中にあって、最後は称名へと収斂せられていきました。そのことは『正法眼蔵』の晩年の作とされる「道心の巻」における、
ただ寝てもさめても仏のみ名を称えたてまつるべし。南無帰依仏……等と称えたてまつるべし
の文にもみることができます。
凡夫は懈怠の心に覆われ、念仏する心も滞りがちなのですが、そんな時でもたとえ機械的にでも一声、南無阿弥陀仏の名号を発する時、その心の状態は一変し、念仏心が生起するのであります。「念仏に懶き人は無量の宝を失える人なり」から「念仏に勇みある人は無量の宝を得たる人なり」(法然上人)へと一変してゆくのであります。
それゆえ田中木叉上人も、たとえば、「じひの華つみうた」の中で、
み名をよぶ 声に心が 乗せられて
よぶたび通う 慈悲のふところ
あるいは、
呼ぶ前は さほど感ぜぬ 大慈悲の
声に心の うつり恋しき
等の歌もみられます。
それゆえ弁栄聖者の「念仏七覚支」の御歌の中でも
声々御名を称えては
慈悲の光を仰ぐべし
身心弥陀を称念し
勇猛に励み勉めかし
(精進覚支の項)
と歌われております。称名は煩悩を破る何よりの手段ですが、実はその手段となる名号の中に目的そのものである阿弥陀仏ご自身がはたらき実現せられてゆくのであります。称名において手段と目的とは不二であります。