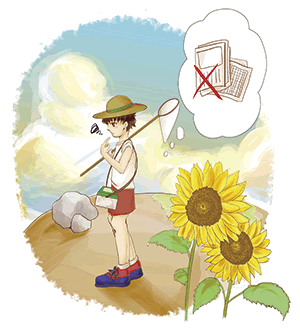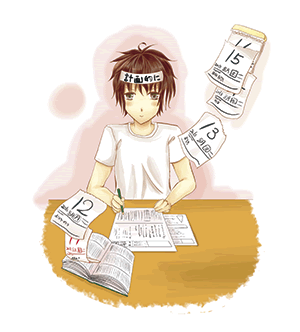関東支部会員 佐々木 有一
四、仏力とは(つづき)
さて、本線に戻りましょう。仏舎利に敬礼するとの建前で唱えられる「舎利礼文」に…入我我入 仏加持故…という文がありますが、この入我我入は仏入我 我入仏が略されたもので縁起の関係を表わしています。内からの自力でなく外から加わってきて自分を充実させ向上させ転換させてくれる何らかの力を感ずることが、誰しもあると思います。この外からの力は、要するに神からの力、仏からの力などと、人間たる自分を超えたものから加わってくるとしか受けとれないものであります。加持、加被、加備などとも表現されますが、密教特有の宗教体験ではありません。密教にはるかに先立つ紀元前後ごろに成立した経典に「般舟三昧経」というのがありますが、すでに仏と人との感応道交の有様が説かれています。
諸仏、とくに阿弥陀仏が面前にましますことを信じて念仏(憶念)すれば仏を見たてまつり、空三昧を得る、とし、この三昧は仏力の成せる所である、すなわち仏の威神力、三昧力、本功徳力によるが故に、と説いています。
いくつかの経文を引いてみますと:
仏を見たてまつらんと欲せば即ち仏を念ぜよ。
阿弥陀仏、今現在したまうを念じ、所聞に随って当に念ずべし。
一心に念ずること、もしは一昼夜、もしは七日七夜、七日を過ぎて以後、阿弥陀仏を見たてまつる。
仏身に三十二相あって悉く具足し、光明徹照し端正無比にして比丘僧の中に在って経を説くことを念ずべし。
仏、いずれの所より来り、我、いずれの所に到るとなしたまう。自ら仏を念ずるに従来する(どこかから来た)ところなく、我もまた所至(どこかへ行くこと)なし。
彼の間の仏刹に生じて見るにあらず、すなわち是の間において坐にして阿弥陀仏を見たてまつる。
念仏を用うるが故に空三昧を得。
是の三昧を證すれば空定となることを知る。
是の三昧は仏力の所成なり。…仏の威神力を持ち、仏の三昧力を持ち、本功徳力を持つ。この三事を用うるが故に仏を見ることを得。
心、仏と作る。心、自らみる、心は是れ仏心なり。
(支婁迦讖訳「般舟三昧経・行品第二」、望月信亨国訳)
龍樹も『十住毘婆沙論』第二章の「入初地品」と第二十章の「念仏品」において般舟三昧を重ねて説いて大変重視しています。観無量寿経(像想観)に、
諸仏如来は是れ法界身なり、一切衆生の心想の中に入りたまう。是の故に汝ら心に仏を想う時是の心すなわち是れ三十二相八十随形好なり、是の心仏を作る、是の心是れ仏なり
とありますのは般舟三昧のことを述べているにほかなりません。善導がこれに「弥陀身心遍法界 影現衆生心想中」と讃を付している(「日中礼讃」)こともよく知られています。ここではたらきかける仏力について善導は大誓願力、三昧定力、本功徳力とよんでいますが、さきの般舟三昧経の三力と大差ないと思います。また善導は念仏に際して親縁、近縁、増上縁の三縁がはたらくことも強調し、その一方で念仏する衆生の側にも至誠心、深心、回向発願心の三心を具えることの大切さも見落とさず、教学が精緻に発展していることを示しています。
いずれにしても仏力が衆生の上に働きかけてくることは大乗仏教の根本原理とも言うべき縁起・空の立場と不可分に結びついた如来の大慈悲といわねばなりません。大乗思想の初期を代表する「八千頌般若経」を現代語訳された梶山雄一教授は仏弟子須菩提が仏陀の威神力の助けをかりて説法を始めるについて、須菩提のそうした説法は「士用果」であると注釈しておられます。「六因四縁五果」という因果関係論が仏教理論の一分野でありますが、士用果はその五果の一つで、成唯識論では「もろもろの作者のもろもろの作具を仮て弁ずるところの事業なり」と定義しています。ある人がある道具を使ってなにかを作ったとか、なにかを実現したとか、要するに人間が作用したことによる果、その果を士用果というわけです。今の場合は作用しているのは仏ですが、理論的枠組みの構成はいずれにもせよ、仏の力の存在は昔から感じとってきたところであり、須菩提の説法もこうした仏の威神力、仏力が加わってのことでありました。
個々の現象は縁起所生のものであり変化してやまない世界ですが、その本質をなす真如・空性は常住不変であり、しかも現象と真如が別々にあるのではないというのが仏教の世界観であり大原則です。拙稿「自他不二への向上み」で略述しましたように、空でありつつ働きがあり、働きがありつつ空である、ということを「真空妙有」といいます。鈴木大拙師はさらに一歩踏み込んで空の世界にこそ大悲の働き(妙用)が豊かに湧き出すのだと「真空妙用」ということを強調されました。このような空の働きは「空用」ということも出来(山口益ほか『仏教学序説』)、いわゆる他力の働き(他力の化用)とはこの空用にほかならないと考えられます。哲学的には空用、宗教的には妙用ということでしょうか。
仏身論の他受用身という考え方も仏の功徳が空定を介して菩薩に及ぶ(回向)ということでありますが、この関係を次第に「摂取」という救済へ寛大化、いいかえれば進化発展させてきたのが仏教の歴史、発達史ともいえましょう。この点はすぐ後に若干触れてみたいと思いますが、そもそも本稿の「仏力と易行」というテーマそのものがその一端ともいえるでしょう。
なお前出「加持」については次のようにも説かれています。仏・菩薩が不思議な力をもって衆生を護ること。仏の大悲の力が衆生に加わり、衆生の信心に仏が応じて、互いに道交すること。日本の密教(空海『即身成仏義』)では仏日の影が衆生の心水に現ずるを「加」(仏の衆生に対するはたらきかけ)といい、行者の心水よく仏日に感ずるを「持」(行者が仏からのはたらきかけを受けとめ持すること)という、とされます(中村元『仏教語大辞典』)。
仏の加被力があらわに衆生にみられることを顕加といいますが、仏・菩薩から人知れぬ冥々のうちに加護を受けること(冥加)もあります。天台宗の『法華玄義』という教えには機と応と顕と冥を組み合わせて四通りに表現しています。顕機とは現世で積む善のこと、冥機は過去世に積んだ善で、この二つの機に顕応と冥応があるといいます。顕応は仏に会うなど目に見える形の利益があること、冥応は仏がひそかに衆生の能力に応じて利益を垂れることでしょう。顕機顕応から冥機冥応まで、ともかくも仏力は加わってくるものと信じることが第一です。その場合いずれにしても仏力がはたらいてくるには衆生の側の、仏に対する称名、憶念、恭敬、礼拝等、つまるところ帰依の心あってのことということが忘れてはならないことであります。
般舟三昧経が明らかにしたことは要するに回向ということでもあります。拙稿「回向から摂取へ」から要点を摘記しますと、亡者への手向けが往々にして回向と受けとられているのが今日の事情ではありますが、本来の回向とはもっと幅広い意義をもっています。パリナーマというのが原語で、変化・転換という意味であり、仏教史的には業報・輪廻の二大原理である因果応報、自業自得を破り、超える考え方として注視すべき教理であります。
無量寿経の古型とされる「大阿弥陀経」という経典があります。紀元頃の成立とされますが、このなかに、法蔵菩薩は無量(兆載永劫)の修行を積んで阿弥陀仏と成りますが、その自己の善業と修行の功徳を善人ならざる人に回向して、彼を仏の国に生まれさせる、とあります。善人ならざる人(悪人)は地獄ではなく仏の慈悲によって安楽国(極楽)に生まれるのでありますから、明らかに輪廻の二大原則は破られています。
回向の転換には二つの型があるとされます(梶山雄一『さとりと廻向』他)。
一つは「方向転換」の回向です。自己の功徳を他へ振り向ける。自作の功徳を他が受ける、つまり自作他受ということになります。
第二のタイプは「内容転換」の回向です。たとえば「小品般若経」は「布施ないし禅定の五徳目が一切智に回向されて布施波羅蜜ないし禅定波羅蜜になる、すなわち『成熟させられ転換され』て、出世間的な超越的なものに転化する」と表現しています。布施、持戒、忍辱、精進、禅定、般若の六波羅蜜は菩薩の修行徳目としてあまねく知られるところですが、この徳目は一つ一つがそのままでは世間的、宗教的な善行にすぎません。ところが般若(智慧)波羅蜜は「智慧の完成・完全なる智慧」であり、それは空の智慧、無上にして完全な智慧であり、仏陀の一切智にほかなりません。すなわち一切智という出世間的な空の智慧によって昇華されることによって、すべて単なる善行は出世間的・超越的なもの、つまり空の働き、仏陀の働きに転化するというわけであります。
回向による救済の典型は阿弥陀仏の働きです。伝統的な解釈によれば、阿弥陀仏は自己の功徳を衆生に回向し(方向転換、自作他受)、衆生はそれによって極楽浄土に往生し、やがて成仏する(内容転換)のでありますから。
阿弥陀仏との対面を願う念仏によって、感応道交・入我我入という仕組みが働きだし、空三昧を得るのですが、ここに空三昧の源流を見ると同時に、縁起所生・空の世界が開かれて回向の概念をも生み出してきたのであります。大乗仏教は仏塔崇拝や仏伝・ジャータカなどの讃仏物語を契機に誕生したといわれますが、他者救済の具体的な仕組みとして、智慧と慈悲そのものとしての仏身論の発展に併行して、その仏と衆生を結びつける回向というかたちを基軸として発展し来たったといえるでありましょう。
もっとも回向の思想は施す側の仏と受ける側の衆生の双方の空定を前提としているために大きな制約を受けています。これを打破せんとする教学が浄土門の「摂取」の思想でありますが、ここでは本論から外れるために詳述は控えますものの、弁栄聖者の光明主義は本有無作の本仏阿弥陀仏を大ミオヤと仰いで新しい仏身観を樹て、新しい仏教公理のもとに成り立っています。そこでは箇条書き的に仏の徳性を列挙する代わりに「独尊」なる一語に集約し、そこから一切知・一切能という属性を引き出して統摂・帰趣の理を演繹し、かくして古来いわれる「他作自受の難」を克服して摂取不捨万機普益の教理を確立されたのであります。詳細は拙稿「大ミオヤの発見――新しい公理をたてた弁栄聖者」ご参照。
仏力の及ぶについても弁栄聖者はみずからの実証から独自の宗教体験を明かされています。衆生の側の「霊恋」を通じて「霊応」、「霊養」などの形で仏力のはたらきかけがあることを、新しい用語を創出して明らかにされました。新しい酒を入れるには新しい革袋が必要であります。
実践論としても般舟三昧を再発見し、入我我入への念仏の深まりの道筋を、古来の七覚支の教えをみずからの実証実体験をもとに具体的に懇切に説き明かし、三昧の方法論を明示されたことも歴史的に特筆すべき業績といわねばならないと思います。
弁栄聖者には「見仏の心的状態」と題する次のような趣旨の文章があります(縮刷版『ミオヤの光』第二巻所収「三昧の巻」)。
吾人の心霊はそもそも絶対の心霊界の分現であり、如来大心海中の霊波の如きものである。三昧発得して見仏ということについても、それは自己の根底大心海より自己の心霊に実現するのである。肉眼に対して、白く冴える玲瓏たる月が雲間より現れるというようなものではなく、また心眼に対して客体として反映してくるものでもない。自然界は人の眼があって物があり、それを太陽の光で視る、という相対的関係であるが、霊界は絶対の世界であり、彼此の別なく大小の分もない。如来の相好荘厳が見えるというのも、絶対より自己の内的霊性に発現したものを、彼処に、彼の空界に投映してこれを視るのである。それは全く遥かの彼処に旭陽赫々として光を放つ如くに現ずるのである、と。
光明主義に沿って念仏を実修するに先立って「如来光明礼拝儀」という勤行式を読誦しますが、その「至心に勧請す」の段では、
…如来の真応身は在さざる処なきが故に 今我身体は 如来の霊応を安置すべき宮なりと信ず…今や己が身を献げて至心に如来の霊応を勧請し奉る 霊応常住に我心殿に在まして転法輪を垂れ給え
とよみ上げます。ここに勧請とは如来の分身たる霊応身をわが身心に請じて、常住の指導を祈ることであります。
いったい光明主義の如来三身の考え方は法身の如来が人や世界を産み活かす「生みのミオヤ」とよばれ、こうして生まれた一切衆生を宗教的に救い育てて真善美の境涯に摂取する如来を報身、「育てのミオヤ」といいます。その報身の分身が応身で、これには応化身と霊応身の二つがあるとされます。応化身は釈尊のことで教え導く「教えのミオヤ」と呼ばれ、肉体があり寿命があって今はおかくれになっています。そのため釈尊は仮応身ともいいます。これに対して真応身というのは報身の一つの態であります。報身如来は衆生を救い育てるために種々様々に御体を分身して、あまねく私共の真正面に在ましておられます。この報身如来の分身を真応身と申しあげ、滅をお示しになることはありません。この真応身が人の信仰の心機に感応してその人を霊化し霊の生命に入らしめる、その当体を霊応身というわけです。これはいわゆる小乗教の「五分法身」、すなわち戒・定・慧・解脱・解脱知見(解脱における知と見のはたらき)の五つの法(徳性)を身体とする者、に当るとされ、人の身内に常住して滅することなし、とされています。私共が勧請し心本尊と仰ぐのはこの霊応身にほかなりません。単に「霊応」というのもほぼ同様の意味と思いますが、「仏力」という観点からすればこちらの方がよりふさわしい語感かもしれません(弁栄聖者『礼拝儀要解』及び『仏教要理問答』)。
感応ということについて弁栄聖者の法話では火と炭のたとえが有名ですが『無対光』には人の霊性は蝋燭のようなもので、人が一心に念仏して念々に如来を憶念するときは如来の心光が人の心霊に燃え移ってくるのである、とたとえられた例もあります。
真応身(ひいては霊応身)は法界にあまねく遍在し、人の信念ある処に随って発得する仏身であり、人はこの感応を得てはじめて「聖き心」によみがえり活きた信仰の生活に入りうるのであります。またこのことは「法身より受けたる霊性を報身によって温められますと、私共の霊性は育てられます。…霊応身が銘々の心の中にお宿りくだされ、私共を親しく導き、説法し、戒めてくださるのであります」と体験的に語られています(『笹本戒浄上人全集』上巻「勧請の祈願」)。
ここまでの記述とさきの引文との関係では、報身は「絶対の如来大心海」に当たり、「吾人の根底大心海」は自己の霊性であり、「絶対より自己の内的霊性に発現」するものが霊応身ということでしょう。見仏とは自己の内に霊応身が現象することであります。縁起的の故に現象学的、ともいえようかと思うのであります。
以上のように仏力について考えてきますと、「易行品」を中心とする『十住毘婆沙論』は結局のところ仏力讃歎をテーマとしてものされたように思えてきます。
(つづく)